国保の給付について
療養の給付
国民健康保険加入者は、医療機関を受診するとき、マイナ保険証又は資格確認書を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)の支払いで診療を受けることができ、残りの費用は国民健康保険が負担します。
医療費の自己負担割合(年齢別)
|
年齢 |
自己負担割合 |
|---|---|
|
0歳~6歳(就学前) |
2割 |
|
6歳(就学後)~69歳 |
3割 |
|
70歳~74歳 |
2割(一般、低所得者) 3割(現役並み所得者) |
- 75歳からは「後期高齢者医療制度」の対象となります。
- 「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満(一人の場合は383万円未満)の場合は、申請により、「一般(自己負担割合が2割)」の区分と同様になります。
入院した場合の食事代
入院した場合の限度額は、診療にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
- 住民税課税世帯(下記以外の人) 510円(一部300円の場合があります)
- 住民税非課税世帯(70歳以上では「低所得者2」の人)90日までの入院 240円
- 住民税非課税世帯(70歳以上では「低所得者2」の人)90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 190円
- 70歳以上で「低所得者1」の人 110円
「住民税非課税世帯」及び「低所得者1と2」の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、国保担当窓口で申請してください。ただし、マイナ保険証の場合は不要です。
また、「住民税非課税世帯(70歳以上では「低所得者2」の人)で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」に差し替える必要があります。該当する場合は、入院日数が確認できる書類(領収書または医療機関の証明書)を持って国保担当窓口で申請してください。
療養費の支給
次のような場合、医療費は一旦、全額自己負担となりますが、国保に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
申請に必要なもの
- 国保の資格確認書等
- 世帯主の印鑑
- マイナンバーが確認できる書類(対象者 及び 世帯主)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写真付きの公的書類)
- その他下記に記載の書類
事故や急病等でやむを得ない理由により、医療機関に資格確認書等を提示できなかったとき
申請に必要なもの
- 診療内容の明細書(レセプト等)
- 領収書
医師が治療上必要と認めた、コルセット等の補装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 補装具の購入に係る見積書、請求書、領収書
骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(外傷性の負傷の場合に限る)
申請に必要なもの
- 明細が分かる領収書
- 医師の同意書(骨折及び脱臼の場合)
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合に限る)
申請に必要なもの
- 明細が分かる領収書
- 医師の同意書
手術などで輸血のための生血代を負担したとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
海外渡航中に国外で治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療内容の明細書(外国語の場合は日本語の翻訳が必要)
- 領収明細書(外国語の場合は日本語の翻訳が必要)
- パスポートなど海外に渡航した事実が確認できる書類
- 海外の医療機関等に照会する同意書
療養費支給申請書 様式
高額療養費の支給
医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。ただし、入院時の食事代やベッドの差額代などは対象になりません。
これまで、毎月該当者に通知を行い、医療機関が発行した領収書等を持参して申請を行っていただいておりましたが、令和7年2月申請分からは手続きを簡素化したため、初回のみ申請書兼承諾書を提出いただけば、2回目以降は手続き不要で上毛町から支給決定通知が送付され、自動的に指定の口座へ振り込まれます。
令和7年2月以降、初めて 「高額療養費」が支給されると見込まれる方には「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書」を郵送しますので、下記の書類をご用意のうえ申請してください。
高額療養費の申請に必要なもの(初回のみ)
- 預貯金通帳など金融機関の口座情報がわかるもの
- マイナンバーが確認できる書類(対象者 及び 世帯主)
- 本人確認書類(顔写真付きの公的書類)
高額療養費支給申請書兼承諾書 様式
国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書 (Wordファイル: 22.2KB)
個人単位で、一医療機関の窓口での支払いは、それぞれの世帯の限度額までとなります。ただし、限度額は所得区分により異なるため、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となる場合があります。ただし、マイナ保険証の場合は不要です。
認定証が必要な方は、国保担当窓口で申請してください。
認定証の申請に必要なもの
- 世帯主の印鑑
- マイナンバーが確認ができる書類(対象者 及び 世帯主)
70歳未満の人の自己負担限度額
70歳未満の人の場合、「同じ人」が、「同じ月内」に、「同じ医療機関」に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
また、過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は限度額が変更されます。
|
課税区分 |
所得区分 |
区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
|---|---|---|---|---|
|
住民税「課税」世帯 |
所得901万円超 |
ア |
252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
|
住民税「課税」世帯 |
所得600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
|
住民税「課税」世帯 |
所得210万円超 600万円以下 |
ウ |
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
|
住民税「課税」世帯 |
所得210万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
|
住民税「非課税」世帯 |
|
オ |
35,400円 |
24,600円 |
- 表中での「所得」とは、基礎控除後の「総所得金額等」のことです。
- 所得の申告がない場合、上位所得者(所得901万円超)とみなされますので、ご注意ください。
世帯で合算して限度額を超えた場合
「同じ世帯」で、「同じ月内」に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合は、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上 75歳未満の人の自己負担限度額
70歳以上75歳未満の人の場合、「同じ月内」に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
外来(個人単位)の限度額(下表の「A」)を適用後、入院分と合算して下表の「B」の限度額を適用します。
また、外来、入院ともに、一医療機関での支払いは、それぞれの限度額までとなりますが、下表の所得区分のうち、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」、「低所得者1」、「低所得者2」に該当する人は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)『平成30年8月改正分』
|
課税区分 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
|---|---|---|---|
|
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
|
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) |
167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
|
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) |
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
|
課税区分 |
所得区分 |
外来の自己負担額 |
外来+入院(世帯単位)「B」 |
外来+入院(世帯単位)「B」 |
|---|---|---|---|---|
|
住民税「課税」世帯 |
一般(課税所得145万円未満等 |
18,000円(年間限度額 144,000円) |
57,600円 |
44,400円 |
|
住民税「非課税」世帯 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
|
住民税「非課税」世帯 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
|
- 「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が「必要経費と控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)」を差し引いたときに0円となる人。
- 「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の人。
高額医療・高額介護合算療養費の支給
国民健康保険と介護保険における年間の自己負担合算額(計算期間:8月1日から翌年7月31日まで)が高額となった場合、申請により下表の自己負担限度額を超えた分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
|
課税区分 |
所得区分 |
区分 |
自己負担限度額 |
|---|---|---|---|
|
住民税「課税」世帯 |
所得901万円超 |
ア |
212万円 |
|
住民税「課税」世帯 |
所得600万円超 901万円以下 |
イ |
141万円 |
|
住民税「課税」世帯 |
所得210万円超 600万円以下 |
ウ |
67万円 |
|
住民税「課税」世帯 |
所得210万円以下 |
エ |
60万円 |
|
住民税「非課税」世帯 |
|
オ |
34万円 |
|
課税区分 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
|---|---|---|
|
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
212万円 |
|
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) |
141万円 |
|
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) |
67万円 |
|
住民税「課税」世帯 |
一般(課税所得145万円未満等) |
56万円 |
|
住民税「非課税」世帯 |
低所得者2 |
31万円 |
|
住民税「非課税」世帯 |
低所得者1 |
19万円 |
上記表中の区分の要件は、前述の「高額療養費」と同様になります。
出産育児一時金の支給
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。原則として、国民健康保険から医療機関に直接支払う「直接支払制度」での支払いとなります。(妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。)
出産育児一時金の支給額
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合 500,000円
- それ以外の場合 488,000円
社会保険等を脱退して半年以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険から給付を受けられます。
葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が死亡したときに、申請により葬祭を行った人(喪主)に支給されます。
葬祭費の支給額
30,000円
申請に必要なもの
- 喪主が確認できる書類(「会葬礼状」または「葬祭費の領収書」)
- 喪主の印鑑
- 喪主の預貯金通帳
葬祭費支給申請書 様式
国民健康保険葬祭費支給申請書 (Excelファイル: 42.5KB)
移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用が発生したとき、申請により国保が審査し、認められた場合は「移送費」が支給されます。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 移送に係る領収書
- 世帯主の印鑑
- マイナンバーが確認できる書類(対象者 及び 世帯主)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021
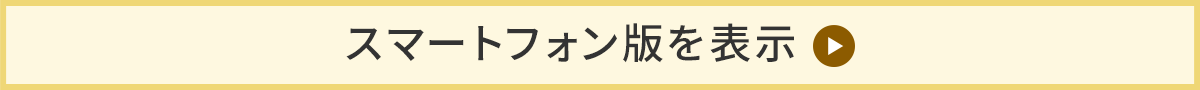





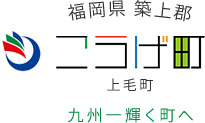
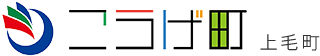


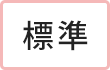
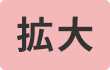



更新日:2025年03月21日